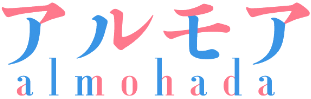FUKO
STORY
午後の暖かな日差しが降り注ぐ、ある日の放課後。
豪奢なベッドの上でうたたねをする少女が一人。
長く艶やかな黒髪はふわりと広がり、磨かれた白磁のような肌をより一層引き立てている。
凛と咲く高貴な花を、時を止めるこの力で自分好みに育てられるのだと思うと、昂る感情を抑えることは到底不可能だった。
小ぶりながらも弾力のある乳肉、固くなった淡いピンク色の乳首、産毛も生えていないつるつるとした割れ目。
一つ一つに快楽を刷り込むように、無垢な身体を舐り弄ぶ。
最後に柔らかな大陰唇をかき分け、膣肉の感触を竿で確かめると、興奮は頂点へと達した。
あの日、目に焼きついたのは、本能的に他者を見下す支配者のような表情。
それは、名家に生を受けた“本物のお嬢様”だけが持つ、揺るぎない威厳であった。
凡俗の者が決して触れることはできない、美しくも遠い存在。
そんな娘を己で手入れし、水をやり、ゆっくりと手折ることができたなら…
何度交わっても、その楽しみが薄れることはなかった。




――彼女を初めて見たあの日から、一年余りの歳月が流れた。
度重なる責めを受け続けた彼女の肉体と精神は、いつしか快楽の虜となってしまっていた。
今では寂れたアパートの一室で、嬉々として自ら腰を振っている。
彼女のために用意した、ウェディングドレスを模したランジェリーが、身体の上下に合わせてひらひらと宙を舞う。
白い布が肌を滑るたび、妖艶な光を放つ。
それはまるで、開ききった白百合が蜜を滴らせるかのようだった。
肉を叩く乾いた音と、体液の跳ねる淫靡な音が響き混ざり合う。
せがむように肉棒を咥えこんだ膣穴は、子種を搾り取ろうとしがみついて離さない。
そしてそれに応えるように、腹の奥底で滾る熱がゆっくりとせり上がってくる。
かつて生徒会長に任命されるほどの知性と気品を備えていた彼女も、今ではその面影すらない。
気高く理想を見据えていたその瞳も、今はただ虚ろな輝きが揺らめくだけだ。
その光景に酷く下卑た愉悦を感じながら、彼女の奥に白濁色の愛を流し込んだ。